ゲームジャンル徹底解説!分類の定義や代表作までをご紹介!
2024年12月25日

ゲームのジャンルと言えば、RPGやアクション、アドベンチャーやシューティングなどがありますが、ほかにも多数の分類があります。そのため、「ジャンルの分け方がよくわからない」という人も少なくないでしょう。
そこで、「ゲームのジャンルを詳しく知りたい」、「夢中になれるゲームを探している」といった人に向けて、ゲームのジャンルを徹底解説していきます。
ゲームジャンルの基本的な分類は?
ゲームの「ジャンル」について考える場合、RPGやアクションなど、ゲームソフトの内容について語ることが一般的で、当コラムも全体としてソフトの内容を中心にジャンル分けしています。
とはいえ、ハードウェアによる分類も行われているので、この項目で簡単にハードによる分け方を解説しておきます。
ゲーム機での分類
プレイするゲーム機でゲームを分類する場合、以下の4種類があげられます。
・スマートフォン(スマホ)ゲーム
・PCゲーム
・コンシューマーゲーム(家庭用ゲーム機でプレイするゲーム)
・アーケードゲーム(ゲームセンターなどのアミューズメント施設でプレイするゲーム)
ちなみに、角川アスキー総合研究所が発表した『ファミ通ゲーム白書2023』によると、2022年の日本国内のユーザー数はアプリゲームが3959万人と圧倒的に多く、次いで家庭用ゲーム(コンシューマー)ゲームユーザーが2856万人、PCユーザーは1406万人となっています。この結果を見ると、日本で最もプレイされている数が多いのはスマートフォンゲームであることがわかります。
とはいえ、近年はPCと家庭用ゲーム機の両方でプレイできる「クロスプラットフォーム対応」も増えていますし、PCとスマートフォンの両方でアカウント共有できるゲームも多いので、ハードウェアの垣根は低くなっているとも言えます。
プラットフォームでの分類
「プラットフォーム」という言葉には複数の意味があるため、混乱が起こりがちです。まずIT業界ではWindowsやMacOS、iOSやAndroidなど、OSのことをプラットフォームと呼びます。
一方のゲーム業界では、ゲームをプレイするためのハードウェアを指すことが多く、この場合PlayStationシリーズやNintendo Switch、Xboxシリーズなどで分類されます。とはいえ、ゲーム業界でもOSをプラットフォームとする考え方もあります。
さらに近年は、SteamやOriginなどのゲームのダウンロードやプレイする環境を整えているサイトも、PCゲームプラットフォームやオンラインゲームプラットフォームと呼ばれているので、ひと口に「プラットフォーム」と言っても何を指しているかは前後の文章や会話の流れに注意する必要があります。
ここではゲームをプレイするハードウェアをプラットフォームとして、以下に代表的なものをあげます。
・PlayStationシリーズ
・Nintendo Switch
・Xboxシリーズ
・PC
ゲームジャンルの紹介

ここからは、ゲームの内容に着目して分類した「ジャンル」を紹介します。
アクションゲーム
『スーパーマリオブラザーズ』など、アクションによってゲームを進めていくジャンルです。『ストリートファイター』シリーズなどの格闘ゲームもこれに該当します。アクションゲームは、瞬時の状況判断や素早く的確な操作が求められることを特徴としています。そのため、テクニックや反射神経を使ってゲームを進めることが好きな人におすすめです。
ロールプレイングゲーム
ロールプレイングゲーム(RPG)と言えば、『ドラゴンクエスト』シリーズや『ファイナルファンタジー』シリーズなど、探索と発見、冒険や戦闘を扱うことが多いジャンルです。このジャンルでは、アクションゲームのように瞬時の操作を求められることはほとんどないので、自分のペースでプレイを進めたい人におすすめです。(ただしアクションRPGのようにアクション要素が強いものもあります)
また、MMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Game)やMORPG(Multiplayer Online Role-Playing Game)もRPGの一種です。どちらもオンライン環境を利用して、多人数によりマルチプレイのRPGを楽しむジャンルです。MMORPGとMORPGの違いは明確ではありませんが、MMORPGが数百人から千人規模で同時プレイすることに対して、MORPGは数名のチームで行動することが多いです。
MMORPGの代表作としては『ファイナルファンタジー14』『ファイナルファンタジー11』や『黒い砂漠』が有名です。一方、MORPGでは『ファンタシースターオンライン』シリーズや『ディアブロ』シリーズが広く知られています。
アドベンチャーゲーム
「アドベンチャー」という言葉は「冒険」を意味するので、言葉だけを聞くとアクションゲームやRPGと混同されがちです。しかし実際のアドベンチャーゲームは、謎解きや推理などを中心としていることが一般的です。『逆転裁判』シリーズや、『ダンガンロンパ』シリーズなど、有名シリーズが豊富にあり、論理的な思考を好む人におすすめしたいジャンルです。
シューティングゲーム
「シューティングゲーム」の始祖的存在と言えば、1978年に登場して社会現象にもなった『インベーダーゲーム』です。その後もシューティングゲームというと戦闘機などで多数の敵を撃ち落とす『アフターバーナー』のようなタイトルが主流でした。しかし、1990年代後半に登場したFPSが2000年代以降は大きな人気を占めるようになり、2024年現在はシューティングゲームと言えばFPSかTPSを思い浮かべる人が多くなっています。
FPSは一人称視点のゲームで、プレイヤーが操るキャラクターの全体像は見えず、銃器を扱う手だけが見えるスタイルが一般的です。FPSはプレイヤー自身が戦闘に参加しているような没入感が魅力です。代表的なタイトルとしても『エーペックスレジェンズ』や『PUBG』、『バトルフィールド』や『コール・オブ・デューティー』など、世界的に有名なタイトルが多数存在します。
一方TPSは三人称視点なので、プレイヤーが操るキャラクターの全体像を視認可能です。TPSにも『フォートナイト』や『荒野行動』など、世界に知られるタイトルが数多くあります。
また、FPSやTPSよりは少ないですが、弾幕シューティングゲームや横スクロールシューティングゲームなども根強い人気があります。
シミュレーションゲーム
歴史や会社経営、街づくりや恋愛など、何らかの設定の下で、プレイヤーが選択した要素を反映していくゲームです。戦時下の拠点攻略や、恋愛の成就、スポーツの勝利など多様な設定があります。シミュレーションゲームには多数の有名タイトルがありますが、『信長の野望』シリーズや『シムシティ』シリーズ、『ときめきメモリアル』シリーズなどが特に広く知られています。
ストラテジーゲーム
ストラテジー(strategy)とは戦略や策略を意味する言葉で、ゲームとしても戦略性を楽しむジャンルです。シミュレーションゲームと似た点がありますし、シミュレーションゲームの一部とする考え方もあります。
また、ストラテジーは大きくはターン性ストラテジーとリアルタイムストラテジーに二分されます。ターン性ストラテジー(TBS)はいわゆるターン性でゲームが進行していくので、時間に追われずに戦略を考えることができます。一方リアルタイムストラテジー(RTS)は名称の通りリアルタイムでゲームが進むので、ゆっくり考える時間はありません。そのためじっくり戦略を考えたい人にはターン性ストラテジーが向いていますし、リアルタイムの緊張感を味わいたい人ならリアルタイムストラテジーがおすすめです。
ターン性ストラテジーの代表作としては、『大戦略』や『バハムート戦記』などがあります。また、リアルタイムストラテジーの有名タイトルとしては『ピクミン』シリーズや『スタークラフト2』などが広く知られています。
サンドボックスゲーム
サンドボックスは「砂場」を意味する言葉で、砂場で好きな形状を作り続けるような自由さが特徴のゲームです。ストーリーやクエストなどはほとんどなく、ゲーム内で何をするかもプレイヤーが自由に選択できます。
『Minecraft』や『テラリア』などの代表作があります。
カードゲーム
カードごとに設定された能力で相手と対戦するゲームです。魅力的なカードを収集しながらデッキを強化していく楽しみがあります。『Magic: The Gathering』『遊戯王』といったリアルカードゲームがデジタルゲームになったものや、デジタル発祥の『ハースストーン』『シャドウバース』などがあります。
レースゲーム
自動車やバイクなどの乗り物を駆使して順位やスピードを争うジャンルです。ひとくちにレースと言っても、ファンタジックなものやコミカルなものもある一方、実在するレーシングカーやバイクを登場させて、サーキットやエンジン音など細かい点までリアルさを追求するタイトルもあります。
キャラクター性やファンタジックなレースゲームの代表作としては、『マリオカート』シリーズは世界的に有名です。年齢性別を問わずプレイできるので、ファミリーゲーム、パーティーゲームとしても高い人気を誇っています。
一方リアルさを追求したレースゲームには『グランツーリスモ』シリーズや『WRC』シリーズなどがあります。この2タイトルはeスポーツの種目としても活用されており、世界中に多くのプレイヤーが存在します。
パズルゲーム
ルールがシンプルなものが多いので、年齢層に関係なく広くプレイされています。また、短時間でも気軽に楽しめることから、通勤、通学中や休憩時間などにプレイする人も多いようです。『テトリス』や『ぷよぷよ』などの落ち物パズルゲームが代表的な存在となっています。
音楽・リズムゲーム
ゲーム内の音楽やリズムに合わせてボタンを押し、タイミングがあっていることなどで得点していくゲームです。いかにミスをしないかを問うゲームなので、ハイスコアを狙う楽しみがあります。『太鼓の達人』シリーズや『ビートマニア』シリーズなどが広く知られています。
人気があるゲームジャンル5選
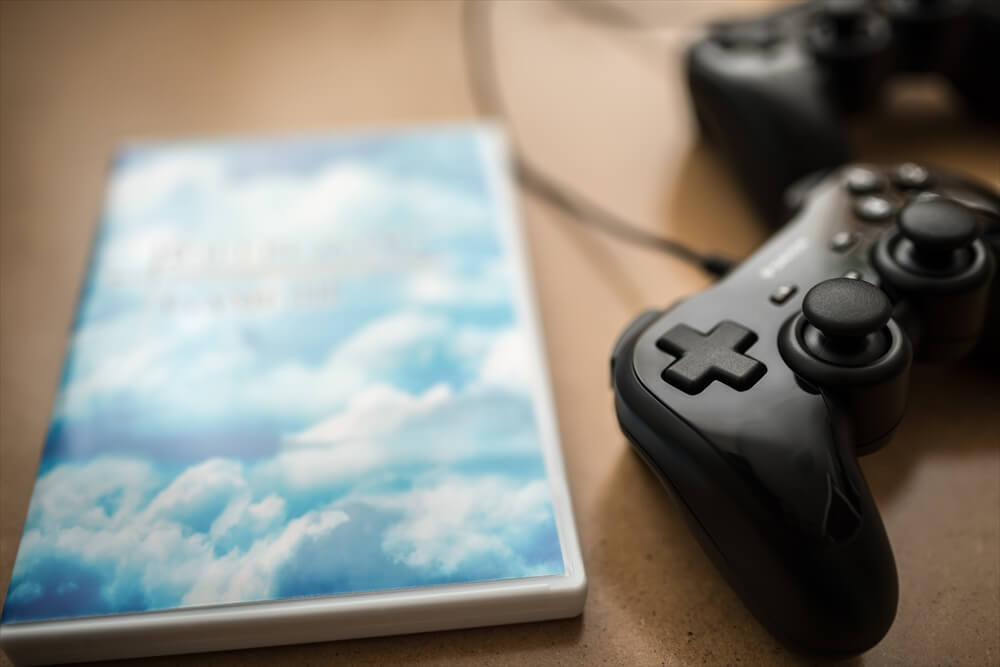
ここでは、株式会社アクロスソリューションズ デジタルマーケティング事業本部が2023年2月に行った「ゲームソフトに関する意識調査」から、特に人気があるジャンル5選を解説します。上記の調査で、ゲームを買ったことがある人に確認した、購入したことがあるジャンルの上位5位は以下の5ジャンルでした。
・RPG(ロールプレイングゲーム)
・アクションゲーム
・パズルゲーム
・シューティングゲーム
・シミュレーションゲーム
各ジャンルを選んだ人は以下のような趣旨のコメントを発しています。
RPG(ロールプレイングゲーム)
上記の調査で、51.8%で1位になったのがRPG(ロールプレイングゲーム)です。
RPGを好む人は、「展開にワクワクしながらプレイするのが好き」、「世界観に没頭できるタイトルが多い」、「魅力的なキャラクターが多い」などの意見を語っています。
アクションゲーム
アクションゲームはランキング2位で、47.6%でした。
アクションゲームを選んだ人は、「深く考えずに楽しめる」、「難しい場面をうまくクリアできた時の達成感が好き」といった感想を述べています。
パズルゲーム
第3位はパズルゲームで、比率としては30.5%でした。
「単純で気軽にプレイできるので楽しい」、「遊びながら脳トレできる」、「暇つぶしに最適」といった感想をもつ人が多いようです。
シューティングゲーム
シューティングゲームは28.5%で第4位となっています。
このジャンルを押している人は「ひたすら敵を倒していくことにハマっている」、「チームプレイが面白い」、「自分のスキルが問われる」といった意見を述べています。
シミュレーションゲーム
シミュレーションゲームは第5位で26.9%でした。
「『信長の野望』などで自軍を強くしていくのが楽しい」、「展開にワクワクする」、「ゲームでしかできないことを達成できる」といったユーザーがシミュレーションゲームを推しています。
プレイヤータイプ別で選ぶゲームジャンル

ここからは、プレイヤーのタイプに注目しながらゲームのジャンルを解説します。
ライバルと競争したい人向け
対戦相手と競って勝利する喜びを得たい人には、オンラインFPSやTPSなどのシューティングゲームやスポーツゲームなどがおすすめです。また、格闘ゲームやレースゲームなどもライバルとの戦いに勝利する喜びがあるでしょう。さらに、目先の対戦で勝利するだけでなく、ランキング上位に入る喜びがあるゲームも多いので、それぞれの目標を見つけやすい点もこのジャンルのメリットです。
冒険大好きな人向け
「冒険が大好き」という人におすすめしたいのは、オープンワールド型のゲームです。このタイプのゲームは、クリアする順序が示されないことを特徴としています。そのため、育成がほとんど進んでいない段階でボス級の強力な敵に遭遇して逃げ出すしかない、といったケースもあります。現実社会が人の成長を待ってくれないように、ある意味本当の冒険に近い体験ができます。
広大な世界観とストーリーが好きな人向け
ストーリー重視で、細かく作りこまれた世界観を味わいたい人には、ロールプレイングゲーム(RPG)がおすすめです。日本のゲームはRPGとともに発達してきたと言ってよいほどの歴史があります。そのため、往年の名作シリーズが多数存在する一方、最新の人気タイトルも堪能できるジャンルです。
また、MMORPGであれば数百人から数千人が同時プレイする点でほかのジャンルにはない「広大さ」があります。
細かい戦略を練りたい人向け
手先のテクニックや反射神経より、戦術や戦略をじっくり練ってゲームをプレイしたい人には、ストラテジーゲームをおすすめします。自軍の配置や使用する武器、敵への攻め方や補給線の確保など、緻密さで勝負したい人に、ストラテジーゲームは向いています。
また、ストラテジーの中でも、じっくり戦略を練りたい人にはターン性ストラテジー、リアルタイムの緊張感を楽しみたい人にはリアルタイムストラテジーをおすすめします。
仲間と共闘したい人向け
ソロプレイよりもチームでの戦いを求める人におすすめしたいのは、MMORPGやFPS、MOBAなどです。チーム戦においては、それぞれの役割を踏まえることや協調することが重要ですから、ひとりで行うプレイでは味わえない喜びがあります。
自分だけの世界・創造したい人向け
自分だけの世界に浸って、創造的な行動を続けたい人なら、サンドボックスゲームやパズルゲーム、シミュレーションゲームをプレイしてみてはいかがでしょうか。
サンドボックスゲームは何事にもとらわれずゼロから創造したい人に向いていますし、パズルゲームは与えられたルールの中で思考することが求められます。また、シミュレーションゲームはプレイヤーの行動で世界が変わることを体験できます。
個人制作でも売れる?ゲームジャンル

この項目では、個人で制作したインディータイトルでも売りやすいジャンルを検討します。特に着目した点を以下に列挙します。
・広告費、開発費用をかけずに作成できるもの
・ダウンロード数、単価が高いもの
・制作の難易度が低いもの
・独自性や個性が出せるもの
開発費用と広告費
個人制作では、開発や広告にかけられる費用に関して大手が制作するゲームに対して圧倒的に不利です。そのため、巨大な費用をかけて開発されがちなRPGで個人が大きな利益を上げることは困難と考えた方がよいでしょう。
ダウンロードと単価
個人制作で「売れる」ことを目指すのであれば、ダウンロード数を上げやすいジャンル、単価を上げやすいジャンルに着目する必要があります。
脱出ゲームは少ない開発費でもある程度の完成度を目指せるので、インディーゲームに向いています。比較的女性のダウンロード数が多いことに着目して、女性プレイヤーをターゲットにするとさらに利益向上を目指せるでしょう。
一方、男性のダウンロード数が多いのは放置、クリッカーゲームです。シンプルで作りやすい割に課金要素を無理なく導入しやすいなど、インディークリエイターに有利な点が多数あります。
制作の難易度が低い
制作の難易度が低い=作りやすいほど、開発費を改修しやすいメリットがあります。そのため、壮大な世界観を作りこむことが一般化しているRPGを、少ない費用で作るとどうしても見劣りするものしかできません。これを踏まえると、売ることを目的とする以上は個人でRPGを作ることは避けた方が良いでしょう。
個性や独自性
個人制作では開発や広告に費用をかけにくいですから、いかにアイデアで勝負するかが利益向上のカギです。そこでおすすめしたいのは、ノベルゲームを基本として独自のアイデアをプラスすることです。
例えばホラー要素をもつノベルゲームであれば、開発費が安いメリットがあります。また、テキストを上手に利用できればホラー性を高めることもできますから、個人制作におすすめのジャンルです。
まとめ
ゲームのジャンルを徹底的に解説し、プレイヤーから見てどのようなジャンルが人気を獲得しているのかをまとめました。また、個人制作で利益を上げやすいジャンルにも言及していますので、ゲーム開発をする人も参考にしてください。
実際のゲームは複数のジャンルにまたがっていることが多く、分類しにくいものも少なくありません。とはいえ、ある程度ジャンルごとの特徴を知っていれば、自分にあうタイトルを選びやすいので、ぜひ折に触れてジャンルに着目することをおすすめします。

